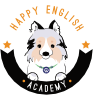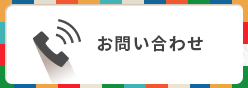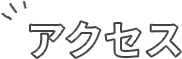目次
- 1 こどもの運動神経は、12歳までで決まる!
- 2 こんな悩みを持っていませんか?
- 3 ゴールデンエイジ
- 4 ゴールデンエイジとは神経の成長期
- 5 プレゴールデンエイジは楽しみながら出来るスポーツに挑戦
- 6 ゴールデンエイジでは色々なスポーツに挑戦
- 7 昔遊びはゴールデンエイジにおすすめ!
- 8 鬼ごっこ
- 9 ボール遊び
- 10 運動神経は「遺伝」するのでしょうか?
- 11 自分は運動が苦手だったから、自分の子供も苦手なはずと考えていませんか?
- 12 「運動神経が悪い」と決めつけていませんか?
- 13 「勉強」と「運動」に相乗効果あり!
- 14 遊びから体の使い方を学ぼう!
- 15 「遊び」ながら子供の運動能力を育てよう!
- 16 走るのが苦手な子でも速くなるコツ
- 17 かけっこが苦手な子の特徴
- 18 体力がない
- 19 走るときのポイント
- 20 全ての運動の基盤となる体遊び!
- 21 料金表
こどもの運動神経は、12歳までで決まる!
- レッスン日
- 火曜日、土曜日、日曜日
- 対象
- 年少〜小学6年生
- 内容
- コーディネーショントレーニング、協調性、機敏性、洞察力、リズム感を学ぶ
こんな悩みを持っていませんか?
①運動会(徒競走)の参加を嫌がる
②サッカーや野球などで思うように活躍できない
③走るとすぐ転んだり、まっすぐに走れない
ゴールデンエイジ

運動神経は生まれつきではありません。実は子どもの成長期には、神経系が著しく発達する「ゴールデンエイジ」と呼ばれる時期があります。
このゴールデンエイジとプレゴールデンエイジの過ごし方によって運動神経の成長が変わってきます。
ゴールデンエイジとは神経の成長期
ゴールデンエイジの時に運動すると鍛えた部分の能力が発達します。
この時期は、一般的に5歳から12歳までと言われています。同じゴールデンエイジ期であっても運動能力の鍛え方が変わってくるため、5歳から9歳ぐらいまでをプレゴールデンエイジ期、10歳から12歳ぐらいまでをゴールデンエイジ期というように分けられています。適切な鍛え方をすることで将来的な運動神経や運動能力に差が出てきます。
プレゴールデンエイジは楽しみながら出来るスポーツに挑戦
楽しい気持ちを育んであげるのが一番大切です。
チームの勝ち負けがあったりするスポーツではなく、かけっこや、遊び感覚で出来るボール投げなどのスポーツに挑戦させてあげて欲しいですね。
この段階で大切なのは、スポーツをした後の達成感を知ることです。
頑張って乗り切った後の達成感や、勝った時の満足感で心を満たすと自信がつき、その自信が自己肯定感へと繋がっていきます。
運動は楽しい、苦しくても終わった後には喜びがあるということを味わいましょう。

ゴールデンエイジでは色々なスポーツに挑戦
10歳ぐらいになると好きなスポーツがだいたい決まってきます。
運動能力を伸ばすには同じ動きのスポーツを繰り返すのではなく、体全体を動かすことも重要です。
神経は全身に存在しています。そして、その神経を発達させるにはあらゆる動きで刺激する必要があります。
1つのスポーツに限定せずにいろいろなスポーツに挑戦させてあげるのが望ましいです。
野球やサッカー、バトミントンなどそれぞれのスポーツごとに体の動かし方が違いますから、機会があるごとにどんどん体験させてあげましょう。
昔遊びはゴールデンエイジにおすすめ!
ゴールデンエイジにおすすめなのは昔遊び。いろいろな動きをしてあらゆる神経を刺激するのにおすすめです。
楽しみながら体を動かすことが、子どもの喜びや楽しさにつながり、運動することへの抵抗感をなくすポイントになります。
鬼ごっこ
ほかの人が逃げている方向を見極めて走る向きを変えたり、歩いたり、動きのバリエーションは意外にたくさんあります。
鬼になった場合も、ほかの人の動きを見ながら走る速さや向きを変えるので、瞬発力も一緒に鍛えられる理想的な遊びです。
ボール遊び
ボール遊びは、体を動かしながら集中力を鍛えていきます。
ボール蹴りであればボールの行き先に集中しますし、ボール投げなら何回キャッチすれば勝ちというルールを決めれば、成功体験を積むこともできます。

日本の子供たちの体力が低下していることは、既にニュースなどで報道されているのでご存知だと思います。
ドッジボールなどをするとボールを顔にぶつけてしまう。
転んでも手が出ないため頭を打ってしまう。さらに体幹がないため、姿勢を正して座っていられない。
小学校では平仮名や九九を覚えるカリキュラムを組まれていますが、「鉄棒の逆上がりを何年生までにできるようにする!」という明確なカリキュラムが体育で組まれているでしょうか?
勉強して覚えたことはノートにまとめたり、発表したりして出力する機会があります。スポーツで練習する時によく「身体に覚えこませる」とよく言いますが、筋肉に記憶装置はありませんから、筋肉は脳の指令のままに動くだけなのです。
ただ、繰り返すことにより、脳に記憶させているのです。例えば、骨折したとします。歩き方や体の動かし方が変わる場合があります。
これは長期間、同じ動作を繰り返した結果、脳がそれを記憶したということになります。
運動神経は「遺伝」するのでしょうか?
自分は運動が苦手だったから、自分の子供も苦手なはずと考えていませんか?
“運動オンチ”は遺伝しません。もちろん得意・不得意はありますが、「最初からできる」という子供は1人もいないのです。
「運動はできるけれど、勉強は苦手」または「勉強はできるけれど、運動は苦手」といったように考えていませんか?
運動も勉強も、「頭で行うもの」なのです。むしろ運動ができる子は勉強もできるようになるということは、多くの研究で実証されています。
「運動神経が悪い」と決めつけていませんか?
東京大学の深代千之教授は、勉強も運動も、できるかどうかは「生まれた後の環境、つまり『やるかどうか』で決まってくるもの」と言います。
飲み込みの早い子や遅い子といった個人差はあるものの、生まれつき何でもできる子はいないですよね。
この発達段階の個人差は、個性なのではないかと私たちは考えています。
たとえば、小学校で見られる運動の得意・不得意の差は、小さい時に身体の動かし方を経験しているかどうかによって決まってくるでしょう。
初めてだからうまくできない」だけで、それは勉強と同じなのではないでしょうか?
深代教授は、「運動ができる・できないも『脳の記憶』なので、運動の巧みさも頭で行うもの」と言います。
つまりは勉強と同じということですね。
運動も勉強も頭でするものという考え方に変えると、子供が持つ可能性が大きく広がってくるはずです。
「勉強」と「運動」に相乗効果あり!
「走る」「投げる」「打つ」「跳ぶ」などのいろんな動作を脳に覚えこませておくと、スポーツの場面でも適用されます。
これは、英語でも同じことが言えます。単語や熟語を覚えておくと、英会話やリスニングの時に使えるわけです。
勉強と運動においても、「できないことができるようになる喜び」をたくさん味わうことにより、自己肯定感が高まっていきます。
そして、さまざまな研究により「運動ができると勉強もできる」という相互関係も実証されています。
遊びから体の使い方を学ぼう!
運動を「遊びの延長線上にあるもの」として考えることが大事です。
そのためには、4〜5歳のときから「跳ぶ」「投げる」「蹴る」といった基本動作を遊びから学び、スポーツへとつなげていきましょう。
私たち人間は最初に頭が大きくなり、幼児期は脳の中に神経がどんどん張り巡らされていくそうです。
この時期にさまざまな動きをすることにより、その動作が脳に記憶されるようになります。
同じ動きを繰り返す中で脳に記憶としてとどまります。これは勉強でも、ボール投げでも、鬼ごっこでも、すべて同じだと言われています。
このように、遊びを通じて“身体の動かし方”を脳に記憶させていくことが、その後の子供の成長において大きく役に立つのです。
「遊び」ながら子供の運動能力を育てよう!
例えば、「どうしたらもっと強く投げられるか」「どうしたらまっすぐに投げられるのか」を一緒に考えながら練習していくと、だんだん体と脳が記憶をしていきます。
そして「体幹」を鍛えるには「おしり歩き」がオススメです。お尻を床につけて膝を軽く曲げ、手は床につかないようにして身体をくねくねさせて速さを競います。
これは普段の生活やスポーツ競技ではあまり気にしない「体幹」の使い方を学ぶことができます。走る力を向上させるのには、非常に効果的なトレーニングです。
いろいろな遊びを通じて「身体の動かし方」を身につけておくことが大切です。
またスポーツに親しんでいくことが、「考える力」や「記憶力」、すなわち学力の向上へと繋がっていきます。
身体を動かすことで「できないことができるようになる」という体験をします。その自信がやがては自己肯定感へとなっていきます。
健康・体力増進といった直接的な効能だけでなく、スポーツには「脳の発達」を促すチカラがあります。
体を動かすが楽しいと思えるような環境が大切です。体を動かすことが楽しい、気持ちいいことだと分かれば、子どもも自然に運動が好きになるはずです。
走るのが苦手な子でも速くなるコツ
かけっこが苦手な子の特徴
なぜ速く走れないのか?何を直せばいいのか?
まず走っているときの姿勢をチェックしましょう。
- 上半身を左右に揺らしていませんか?
- 首を左右に振っていませんか?
- 腕を前後に振っていますか?
- 足をしっかりと前に出していますか?
体の軸がしっかりとしていないと、上半身が左右に触れてしまい、力も左右に分散されてしまうため前に進む力が弱まってしまいます。
体力がない
スタートは遅くないのに、半分過ぎた頃から急にスピードが遅くなってしまう場合があります。
これはゴールまで走りきる体力がないことや、ペース配分が上手くできていないことなども考えられます。
また、運動の経験が少ない場合も考えられます。
小さい頃に公園などで遊んだ経験が少ない、全速力で走ったことがないという子供にいきなり運動会で速く走ることを期待するのは無理があります。
体の使い方、足の運び方など普段から体を動かしたり、走る練習などの経験をしたりすることによって、自然と身につくことが多いです。
走る速さは運動の経験とも関係していると考えます。
走るときのポイント
- まっすぐな姿勢
- 足のつく位置
- つま先から着地
- (1) 正しい姿勢
-
- 顔はしっかりと前を向く
- 背筋を伸ばす
- 胸を張る
しっかりと前を向いて、スタートラインに立つことが重要です。
運動会などでの競争に慣れていないと、スタートの時によそ見をしてしまい、出遅れたりすることがよくあります。
「音が鳴ったら、すぐに走るんだよ」「前をしっかりと向く」など分かりやすく伝えてあげましょう。
- (2) スタートダッシュ
-
スタートダッシュは、最初の一歩目の位置が大事!
足が自分の体より前に出ていたり、かかとが地面に先についたりしていませんか?
まっすぐな姿勢のまま、体を前に倒します。頭から足まで一直線になるようなイメージが大事です。まず、前足のつま先に体重を乗せます。この状態から走り出せば、素早いスタートダッシュが切れます。
幼稚園、小学校低学年の場合は、スタートダッシュの時点で勝負がついてしまうことが多々あります。
逆にスタートダッシュに成功すれば、勝つ可能性が高くなります。
- (3) 蹴りだす力と腕の振り方
-
自分の利き足を知っていますか?
走るのが苦手な子は自分の利き足を知らない場合が多いです。かけっこ教室に参加して、まず自分の利き足を知りましょう。
走っている間も地面をしっかりと蹴り、ももをあげて前に出す意識をしましょう。
正しい姿勢が身につけば、自然と歩幅も大きくなり速く走るための条件が整っていきます。腕の振り方で走るときの姿勢はかなり変わります。
肩や腕を左右に振ると前に進もうとする力が弱まったり、体の前に腕がきて邪魔になってしまいます。
腕をしっかりと前後に正しく振るだけで走るの少し速くなります。
- (4) 全力で駆けぬけよう
-
速い子と遅い子の大きな違いは、ゴールを駆け抜けているかどうかです。
ゴール地点をどんなスピードで走るかによって、順位も大幅に変わってきます。最後まで走り抜ける練習をたくさんしましょう。
走ることは、スポーツに必要な運動能力を向上させます。
走ることが得意になれば、やがては他のスポーツにも興味も広がり、挑戦してみたい気持ちが芽生えてきます。
かけっこは、コツを知れば、速く走れるようになります。ぜひ一度、お子さまと一緒に練習してみましょう!もうひとつのポイントは、走る時の姿勢です。最初は、低い姿勢を保って走ります。
スピードが上がってきたら、上半身を起こして体をまっすぐにします。着地する時は、つま先からおろし、しっかりと地面を蹴りましょう。
ポイントは、自分の体に近い場所で最初の一歩を踏み出すことです。
全ての運動の基盤となる体遊び!
こどもの頃に体を動かすことの楽しさを知っておくことが、生涯健康で元気に暮らしていくことにも繋がります。 まず心の緊張をほぐし、体の使い方を学びます。体が強張っていれば、怪我もしやすく、能力が存分に発揮できないと考えます。 運動には、ネガティブな気分を発散させ、心と体の緊張をほぐし、睡眠リズムを整えるという作用があります。 1日にたくさん練習して終わりにするのではなく、継続的に体を動かす習慣を身につけていきます。
“継続は力なり”良い言葉ですね!
体を動かしていくことにより、体幹が鍛えられ、集中力が増します。
体幹が強くなると姿勢が良くなり、座ることに抵抗が無くなります。やがては学力向上へ!
『たかがかけっこ。されどかけっこ。』
料金表
| 参加費 |
3,000円 *学童レギュラー会員の方は割引制度あり! |
|---|