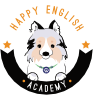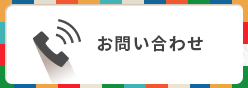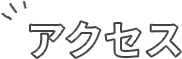好きになると自分から学び出す。得意になるとどんどんチャレンジしたくなる。そんな子供たちの意欲をかき立て、可能性を大きく広げるために、英語、個別指導(国語・算数)、硬筆・書道、かけっこなど楽しく取り組める様々な習い事を用意しています。
英語コース
こども達は、喉がすごく渇いたときに"Water, please."、疲れたときに、"Iʼm tired."、嬉しいときに、"Iʼm happy."。出来るだけ自然な形で、身につけていくことが大切です。「何とかしてこの気持ちを外国人に伝えたい、でも言葉が分からない、どうしよう。」と思った時が一番覚えます。そして必死に使おうとしますし、覚えようとします。またお友達が言っていることを、真似してみます。相手が理解してくれたときに、これさえ覚えたら意思疎通できるかもと子供たちは思うはずです。
まさにサバイバル英語!
子供達は夢中で遊んでいるとき、“勉強中”とは思っていません。 小さい頃は、「遊ぶ」ことから多くのことを学びます。 自分のしていることに興味を持っているので、それが学習だということにも気づきません。学習意欲は遊ぶことでレベルアップ!「短期的、長期的に関わらず、子供たちが遊びを楽しんでいるときには、認知的、社会的、感情的、および身体的にも学習に対する意欲が高まる」との見解もあります。
「遊び」は「学び」、「学び」は「楽しみ」!楽しみのない学び、 強制された学びは単なる苦痛でしかありません。だからこそ既存のカリキュラム通りに進めるのではなく、気持ちに寄り添いながら進めていきます。心と体の成長、五感を十分に動かす経験を積み重ねていくことにより、安定した情緒、身の回りへの関心、自発的に活動する意欲を培っていく事が出来ると考えます。
学びと遊びの関連性。思考を巡らし、想像力を発揮するだけでなく分かること、出来ること、挑戦することの大切さを学んでいきます。幼稚園児の学びとは、新たな発見、理解を深めていきながら、挑戦していくことの喜びを知ることにあると思います。
学び続けるために必要な5つの力
①没頭できる力 ②理解する力 ③表現する力 ④観察する力 ⑤発見する力
個別指導コース(国語・算数)
「分かった」と思えば、それはゴールとなります。
「分からない」と思うから、分かろうと努力するのではないでしょうか?「分かろうとする」という行為は自発的に勉強することに繋がります。「分かろうとする」「わかりたい」という気持ちから、少しでも知りたいという内容に近づこうと努力をするわけです。ここで答えを与えられてしまうと、この作業は打ち切られてしまいます。そこで答えを与えられなければ、そこに近づく努力をするようになります。誰かに聞いたり、調べたりもするでしょう。そこで得た情報や見つけた根拠をつなぎ合わせて想像もするでしょう。自分なりにたどり着いたものを誰かに伝えたり、文章化したりもするでしょう。こうして国語力は養われ、やがては全ての教科の基礎となっていきます。
子供が「分からない」と言える環境が大切
子供の「分からない」を認めらる大人、それに付き合える大人がいる子供たちの中には「国語ができる」子が多いように感じます。では、ここで言う「付き合う」とはなんでしょうか?答えをただ教えてあげることではありません。「何がわからないのか」「どこがわからないのか」を共有していくことにより、考える習慣が身についていきます。「考える力」「考える習慣」こそが国語力なのです。
今の子供たちには、「わからない」状況を認識する時間がない
小さいころからたくさんの習い事をさせている家庭を多く目にします。そして小学4年生ごろから成績が伸び悩むケースもよく見受けます。幼稚園〜中学生までを長年教えてきましたが、様々な相談を受けてきました。特に多いのが、「小学校高学年になってから成績が伸びなくなった」という相談です。「お子さんが小さい頃、どのように「過ごされていましたか?」と尋ねると、毎日たくさんの習い事をさせていたと答える方が非常に多かったです。一方で、学年が上がるにつれてぐんぐん伸びる子もいます。最初は、「授業についていけない」「こんなにたくさんの宿題は無理」とブーブー言っていた子が、一度学習ペースをつかむと頭角を現してくるのです。
硬筆・書道コース
書道は小学生から習い始める子が多い
字が書けるようになり、ある程度の集中力が付いてくるとなると、小学生から習字・書道を習い始めるお子さんが多いです。そうは言っても一番大事なのはお子さん本人のタイミングですから、「やりたい!」という気持ちを大切にしてあげましょう。小学校入学前の年長さんくらいから教室に通い始めるお子さんもいます。
小学校3年生になると、「書写」という授業が始まり、習字は必修科目になります。それまでは硬筆のみの授業だったところに習字が入ってくるので、多くのお母さんたちは小学校3年生に上がるまでに習字・書道セットを準備します。
字が汚くても本当に上達するの?
姿勢や書き方を丁寧に教えます。お子さんを書道教室に通わせたいと考えているお母さんは、ほとんどの人が「綺麗な字を書けるようになってほしい」と考えていることでしょう。教室では、基本となる姿勢から、書き方、書き順などの基礎の部分から丁寧に教えています。定期的に昇級試験などもあり、出される課題に向かって何度も繰り返し文字を書く練習を積み重ねていきますので、続けているうちに字は綺麗になっていきます。
大人の習い事としても人気。大人になってから「綺麗な字が書けるようになりたい」と習字・書道教室に通い始める方も多くいらっしゃいます。 それだけ綺麗な字が書けるということは大人になってからも重視されることです。字のクセが付く前に習い始めるのが良い。大人になってから字のクセを直そうを思っても難しいことが多いのが現状です。書道を習い始めるタイミングで迷っているお母さんは、できるだけ早い段階で始めさせてあげると良いでしょう。
字が綺麗になるだけじゃない!
集中力が身についていきます。習字・書道は、多くの教室が一つの部屋で年齢問わず静かに座って授業を行います。 課題の文字に向かってじっくりと時間をかけて向き合うことで、自宅などではなかなか養うことのできない集中力が身につきます。一つの文字を書くのに精神を統一し時間をかけ集中していきます。一つのことにしっかり集中することは、勉学にも当然生かされます。
「活発で落ち着きのなかったのに集中力がついた。」と言われるお母さんも多数いらっしゃいます。
正しい書き方、書き順、姿勢が身につく
硬筆・書道コースでは、先生が書き方や書き順を基本から教えます。書き順は正しい字を書く上で必要不可欠ですので、綺麗な字が掛けることに繋がってきます。どうやって書けば、左右上下のバランスの取れた字を書けるかを習っていくので、ひとつひとつの文字をきれいに書けるようになります。
教室では習字の時の正しい姿勢から習います。崩れた姿勢では習字は行えません。パソコンやスマホが当たり前の時代で前かがみの崩れた姿勢を正すことが大切です。はじめは慣れない姿勢かもしれませんが、背中を伸ばした正しい姿勢を学ぶことによって、その姿勢のほうが楽になり、自然に体に身についていきます。
かけっこコース
「勉強」と「運動」に相乗効果あり!
「走る」「投げる」「打つ」「跳ぶ」などのいろんな動作を脳に覚えこませておくと、スポーツの場面でも適用されます。これは、英語でも同じことが言えます。単語や熟語を覚えておくと、英会話やリスニングの時に使えるわけです。勉強と運動においても、「できないことができるようになる喜び」をたくさん味わうことにより、自己肯定感が高まっていきます。そして、さまざまな研究により「運動ができると勉強もできる」という相互関係も実証されています。
遊びから体の使い方を学ぼう!
運動を「遊びの延長線上にあるもの」として考えることが大事です。そのためには、4〜5歳のときから「跳ぶ」「投げる」「蹴る」といった基本動作を遊びから学び、スポーツへとつなげていきましょう。私たち人間は最初に頭が大きくなり、幼児期は脳の中に神経がどんどん張り巡らされていくそうです。この時期にさまざまな動きをすることにより、その動作が脳に記憶されるようになります。同じ動きを繰り返す中で脳に記憶としてとどまります。これは勉強でも、ボール投げでも、鬼ごっこでも、すべて同じだと言われています。このように、遊びを通じて“身体の動かし方”を脳に記憶させていくことが、その後の子供の成長において大きく役に立つのです。
「遊び」ながら子供の運動能力を育てよう!
例えば、「どうしたらもっと強く投げられるか」「どうしたらまっすぐに投げられるのか」を一緒に考えながら練習していくと、だんだん体と脳が記憶をしていきます。そして「体幹」を鍛えるには「おしり歩き」がオススメです。お尻を床につけて膝を軽く曲げ、手は床につかないようにして身体をくねくねさせて速さを競います。これは普段の生活やスポーツ競技ではあまり気にしない「体幹」の使い方を学ぶことができます。走る力を向上させるのには、非常に効果的なトレーニングです。
いろいろな遊びを通じて「身体の動かし方」を身につけておくことが大切です。またスポーツに親しんでいくことが、「考える力」や「記憶力」、すなわち学力の向上へと繋がっていきます。身体を動かすことで「できないことができるようになる」という体験をします。その自信がやがては自己肯定感へとなっていきます。健康・体力増進といった直接的な効能だけでなく、スポーツには「脳の発達」を促すチカラがあります。体を動かすが楽しいと思えるような環境が大切です。体を動かすことが楽しい、気持ちいいことだと分かれば、子どもも自然に運動が好きになるはずです。